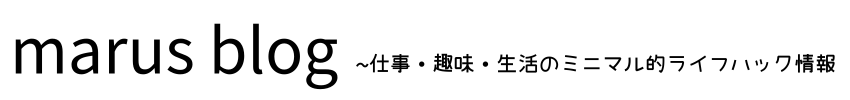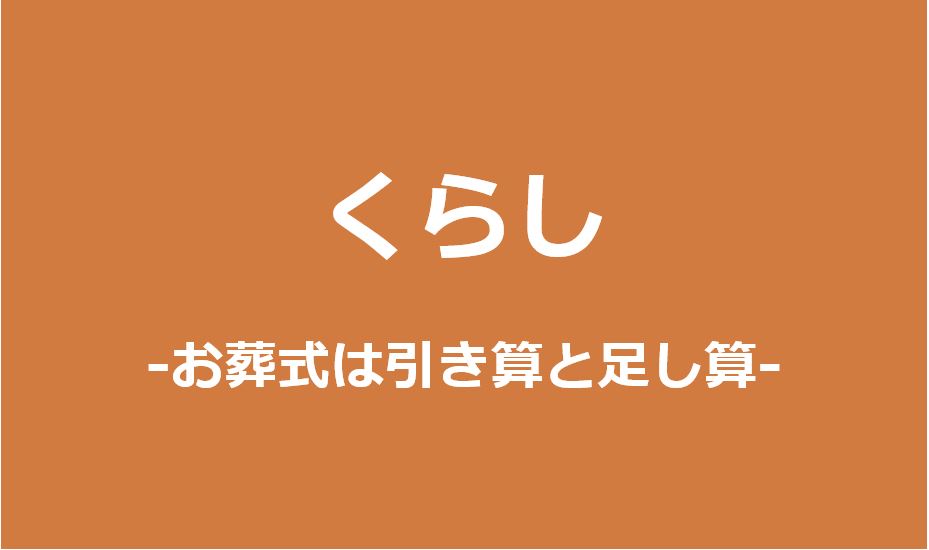
最近の暮らしの中で大きく変わったと感じられるひとつにお葬式があります。家族葬、一日葬、直葬などの言葉が躍りますがその違いがよくわかりません。費用のことになればなおさら。お葬式はいったい幾らかかるのか気がかりです。今回は、よくわからない葬儀の形式と費用について、簡単な足し算と引き算で解説します。少しでもご参考になればうれしく思います。
目次(ページコンテンツ)
お葬式の形式は引き算
最近の日本のお葬式は、「一般葬」、「家族葬」、「一日葬」、「直葬」といった形式があります。それぞれの形式の特徴と違いを引き算で解説します。
一般葬儀の特徴
●一般葬=お通夜+葬儀告別式。
一般葬儀の公式は「一般葬=お通夜+葬儀告別式」と2日にわたって僧侶や神職に依頼して儀式が執り行われます。
故人の家族や親族に一般会葬者が一同に集まり、仏式や神式での通夜式と葬儀儀式が行われます。故人のご冥福をお祈りする宗教的儀式(葬儀)と、故人とのお別れをする告別式が一緒に行われます。葬儀後は斎場に移動しての火葬を行います。
(仏式葬儀の進行例)
| 1.開式の辞
2.僧侶入場 3.読経・引導 4.弔辞・弔電の紹介 |
5.焼香
6.喪主挨拶 7.閉会の辞 8.僧侶退出 |
一般弔問者は通夜のみの参列も常識になってきているようです。
家族葬の特徴
●家族葬=一般葬(お通夜+葬儀告別式)-告別式。
家族中心の家族葬は、一般弔問客とのお別れの儀式が省略されたものと考えると一般葬から告別式を引き算した形、つまり「家族葬=一般葬(お通夜+葬儀告別式)-告別式」と言えます。
家族葬の特徴は故人の家族が中心に行われる葬儀です。親族も少なく、しかも遠方で高齢者も多くなると、お別れはしたいが参列はなかなか難しい状況もみられてきます。
「家族葬=一般葬-告別式」、あえて無理せずに告別式を省略した家族だけの葬儀になります。
一日葬の特徴
●一日葬=家族葬(お通夜+葬儀告別式-告別式)-お通夜
一日葬は、家族葬からお通夜を引き算した儀式と言えます。一般葬も家族葬もお通夜と葬儀告別式または葬儀を二日にわたって行います。一日葬は、お通夜を省略して家族のみの葬儀だけ行うことになります。葬儀後に火葬を行います。
菩提寺があるご家庭では住職(僧侶)との相談が必要になります。菩提寺のないご家庭では、葬儀の際にお経を読んで頂く僧侶を、別途葬儀社を通して依頼する必要があります。
「一日葬=家族葬-お通夜」、本当に家族だけとならば葬儀のみの「一日葬」でよしに。
直葬の特徴
●直葬=一日葬-葬儀。
直葬は葬儀を行いません。火葬のみの供養になります。つまり、直葬から葬儀を引き算した形と言えます。身寄りのない独居老人など、残念ながら一般的な葬儀儀式を執り行えない場合などになります。
最近は、家族はいるもののあえて葬儀をしないというケースも見られ、火葬だけの供養も一般的に認知されつつあるようです。
「直葬=一日葬-葬儀」、火葬だけの供養になります。
お葬式の費用は足し算
お葬式の費用は、儀式に必要な固定費とその他必要に応じて必要となる変動費の足し算になります。
お葬式の費用
●お葬式=固定費+変動費。
お葬式にかかる費用は主に儀式の支度に必要な費用と、その他の費用に分けて考えると整理できます。儀式の支度に必要な基本的な費用は固定費、その他の費用は変動費。
葬儀の固定費は、通夜葬儀に必要な祭壇関係、遺影写真、火葬に必要な棺、骨亀、葬儀社のサービス料などが含まれます。葬儀の変動費は、ご遺体安置費、車の手配、飲食などおもてなし費、香典返しなどの返礼品費、僧侶などへのお礼(お布施)などがあります。
葬儀費用のトータルだけを考えた場合は足し算、当然「直葬<一日葬<家族葬<一般葬」となります。
お葬式の収入
●お香典はお葬式の収入。
お葬式にはお香典などの収入があります。お葬式の収入も足し算になります。つまり、お葬式の収入も「直葬<一日葬<家族葬<一般葬」と言えます。
お葬式の費用と収入を差引して考えれば、葬儀費用の負担は一般葬よりも家族葬の方が抑えられるとは一概に言えないのはこのためです。
香典収入を考えると葬儀費用の負担は「一般葬<家族葬」と考えることもできます。
お葬式の簡素化簡略化事情
故人を火葬して荼毘することは喪主、喪家の責任です。死亡届は国内ならば7日以内と決められています。また、埋葬する際は墓埋法という法律があります。葬儀を必要以上に豪華にする必要もなく簡素化・簡略化は時代の流れでしょう。安易な簡略化で後悔する声も聞かれます。
葬儀はやり直しができない
●あとの供養だけは頼めない。
葬儀をせずに火葬をして納骨を済ませたまではよかった。お墓も要らない海にまいて海洋散骨したものの後で手を合わせる場がなく、供養はこれでよかったのかと後悔したなどの声も少なくないと聞きます。
また、お盆や法要の時期になり、お盆や法要などの供養だけを近くのお寺に依頼しても引き受けてはもらえないという現実、だからといって葬儀をやり直しすることはできません。
後で後悔してしまうということにならないよう、葬儀や供養を安易に考えすぎず注意をしたいところです。
葬儀と供養をどうすべきか事前の相談、検討は必要です。
立場の違いで想いも変わる葬儀
●亡き夫、妻のなげき。
ご主人を亡くされたある奥様のお話です。死を覚悟したご主人は、葬儀は家族だけ祭壇もテーブルに遺影写真だけでいいと言葉を残されていた。家族に負担をかけたくないとの思いからだった。
実際に葬儀となったときに残された奥様は、ご主人の意向があること葬儀は家族葬で簡単にと、それでもと思い亡き夫の親族にも伝え、事前に賛同を得てむかえた。
ところが問題が発生。
実際に用意されたテーブルと遺影写真の祭壇を前にご主人のご兄弟から、話しは聞いていたがこんなんじゃ兄弟があまりにもかわいそうだとクレームを奥さんにぶつけてきたのです。思いもよらない親族の文句は、葬儀を終えた後も引きずり冷たい奥さんのレッテルまで貼られてしまっと困惑するばかり。
死の受け入れ方は立場によってまるで違う、思わぬトラブルも悲しい。
死別の悲しみ
●死別を受け止め前向きに生きるためには時間が必要。
人生の中でもっともストレスに感じるのは家族の死別と言われます。突然の死別とならば死をなかなか受け止められず、悲しみを引きずってしまうというケースもあるようです。
家族の死別を受け止めるためにもお通夜葬儀などの儀式は必要です。さらに、葬儀後の法要やお盆などの供養が心を癒すためにも必要なことでもあります。
葬儀の負担を軽減するだけで葬儀の儀式を省略、簡略すればいいとは言えないことにもなります。豪華にする必要はまったくありませんが、単に省略してよしという考え方も注意が必要のようです。
家族を亡くしたストレスは長く計算できないのです。
私の感想
●激変の葬儀を実感しつつ。
最近のお葬式に参列する際、一般参列者としてはお通夜に参列してお別れをし、葬儀は家族親族が中心と必然的になります。葬儀告別式の告別式をお通夜で行っているということでしょうか。
ご近所の方が亡くなられての葬儀でも、「葬儀は家族だけで行います、お香典などはご遠慮します」と回覧板が回ってきます。ほとんど違和感なく受け止めるようになりましたのもここ数年のお話のように思います。
大自然の動物は自分の死を悟ると家族や仲間の群れから密かに離れ、導かれるようにしてあの世に旅立つとか。あたりまえですが、そこには葬儀の形式や費用などの悩みは存在しない。さてさて、人が一人死ぬってどういうことなんだろうと考えさせられます。
人の死は、形は変われど重さは変わらない、そんな気もします。
(marusblog記事紹介)
http://marus.info/2201-riading/
http://marus.info/2112-shopping-savings-marusblog/
http://marus.info/211124-ending-marusblog/
今回のまとめ
●葬儀の形式は引き算。
家族葬、一日葬、直葬などの言葉が躍ります。その違いを簡単な計算式で解説しました。
(葬儀形式の公式)
・一般葬=お通夜+葬儀告別式
・家族葬=一般葬-告別式
・一日葬=家族葬-お通夜
・直 葬=一日葬-葬儀
●葬儀費用も収入も足し算。
葬儀費用は足し算です。「直送<一日葬<家族葬<一般葬」と言えます。
葬儀の収入(お香典)も足し算。「直送<一日葬<家族葬<一般葬」になります。
葬儀の収支を考えると、必ずしも葬儀費用が「家族葬<一般葬」とならないと分かります。
●安易な簡素化簡略化に注意も。
葬儀事情は激変しています。葬儀は家族葬が普通となり、香典も辞退するともよく耳にします。自分自身が葬儀は要らないと言っても、葬儀をおこない供養をしていくのは残された家族。
後で供養したくても供養ができなくなってしまった、だからといって葬儀をやり直すことはできないなど、安易な簡素化簡略化でトラブル例などもご紹介しました。
葬儀の形式や費用は簡単な計算で説明ができますが、人の死の重さは簡単には測れないものです。
いかがでしたでしょうか?
最後まで読んでくださりありがとうございます。人気ブログランキングに参加中。こちらクリックして頂けましたらうれしく思います。
↓↓↓
![]()
生活・文化(全般)ランキング