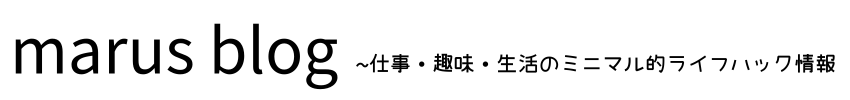子どもの頃の気持ちって、大人になると、どうしてこんなに遠くなるんだろう。「好き」って言葉ひとつで、理由なんていらなかった。一緒にいられるだけで、世界が全部、やさしく見えた、あの感覚。伊藤左千夫の『野菊の墓』は、そんな“失われていく純粋さ”を、声高に語ることなく、胸の奥にそっと置いていく物語だと思う。読んでいるうちに、涙より先に、静かな痛みがやってくる。これは悲恋の話、というより、「正しさを選ぶたびに、置いてきたものがあるんだよ」そんなふうに、ページの向こうからそっと問いかけてくる小説に思うのです。物事を素直に受け入れることもなくなってしまった今、理由のない気持ちを忘れかけているなら。この物語は、静かに教えてくれる気がして、この歳だからこその、そんな気持ちをお届けするわけです。