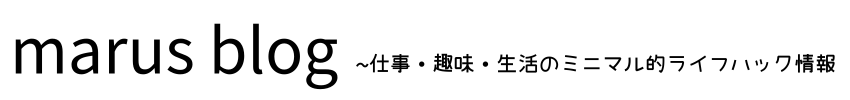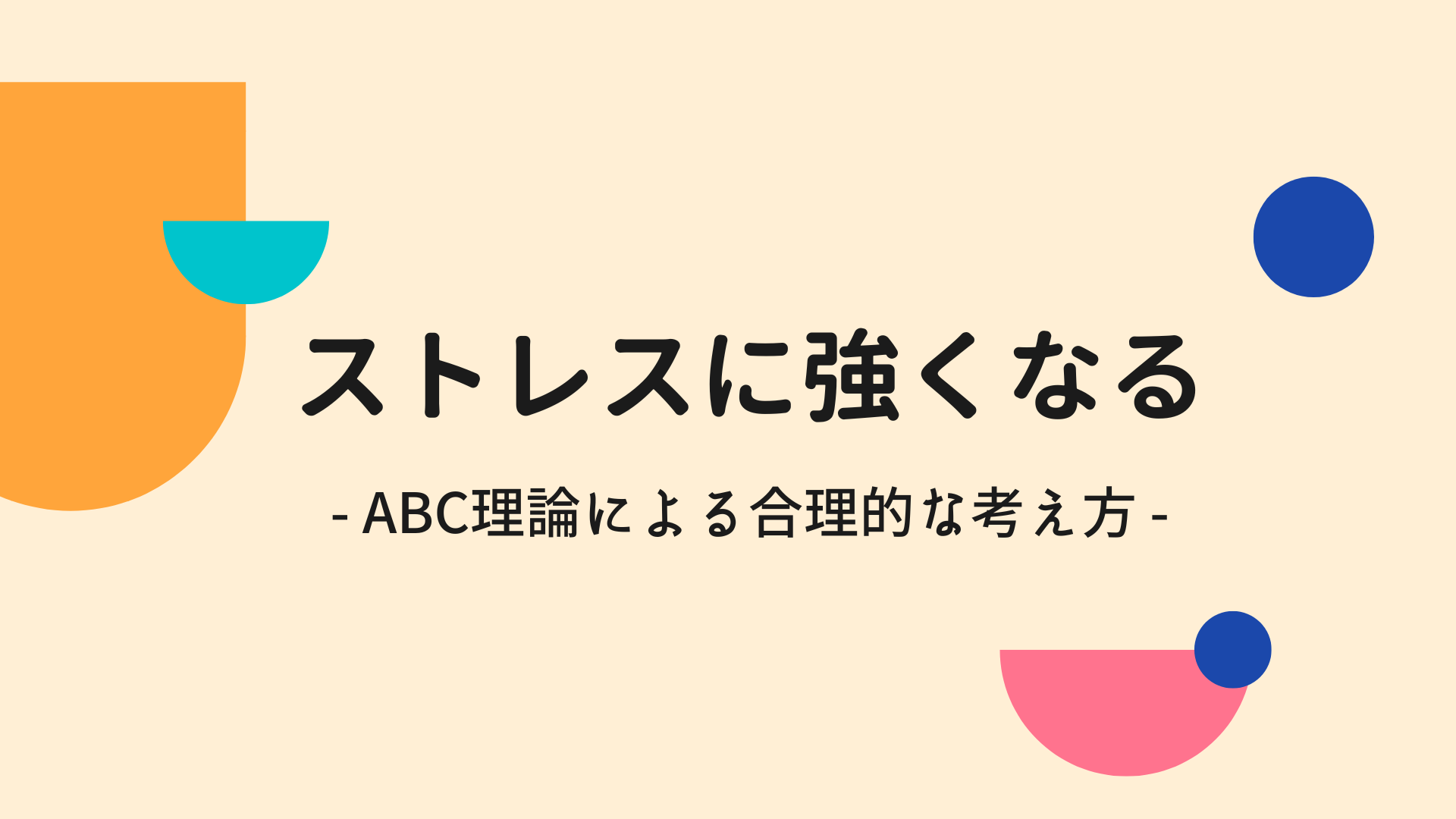
今回のテーマはストレス。不思議なことに同じ出来事でも、ストレスを強く感じてしまう人もいればそうならない人もいる。これってどこが違うのでしょうか?その違いを合理的に説明するストレスABC理論をご紹介します。ストレスABC理論とは、心理学者のアルバート・エリスが提唱した認知行動療法のひとつ。この理論では、ストレスを引き起こすのは出来事そのものではなく、出来事に対する自分の受け止め方や考え方だと考えます。その受け止め方や考え方を知れば、ストレスに強くなるヒントになるかと思います。
目次(ページコンテンツ)
ストレスに強い人と弱い人の二極化
専門家医によると、ストレスに強い人にはある共通点がある。
そして、ストレスに強い人と弱い人の二極化傾向があるというのです。
労働者の5割以上が何らかのストレスを抱えている
厚生労働省の「労働安全衛生調査」による仕事に関する悩みや不安から。
調査によるとストレスを感じている人は、
労働者の5割以上と高い水準にあるとあります。
こちらは、ストレスを感じている内訳。
|
ところが、こうした現状の中でも心を病む人とそうでない人がいることも事実。
ストレスは現代社会の大きな問題です。
読者の皆さんは、どれくらいストレスを感じているのでしょうか?
ストレスが長期間続くと、心身の健康に悪影響を及ぼす。
高血圧や心臓病、うつ病などのリスクが高まると聞くとほっておくわけにはいかないようです。
ストレスを強く感じる人とそうでない人がいることは事実なのです。
ストレスに強い人と弱い人の違いは
同じ出来事でも、ストレスを強く感じてしまう人もいればそうならない人もいます。
ストレスを感じるかどうかは個人差があることは理解しました。
これってどこが違うのでしょうか?
その違いを合理的に説明するのがストレスABC理論です。
この理論では、
|
つまり、自分の考え方を変えることで、
ストレスに対処することができるというわけです。
同じ出来事に遭遇しても人によっては受け止め方は変わる。
|
「人はものごとをではなく、それをどう見るかに思いわずらうのである」(哲学者エピクテトス)
ABC理論とは
ストレスに強いか弱いかは、出来事の「受け取り方」によって変わってくる。
出来事に対する感じ方の違い
ABC理論とは。
ABC理論のA・B・Cとは、次の頭文字から。
|
つまり、
|
出来事ではなく、出来事の受け止め方で結果のストレス反応が変わってくる。
たとえば、
|
「私はダメだ」という信念は自分への否定的評価であり不合理です。
「ミスは誰でもするものだ」という信念は自分への肯定的評価であり合理的です。
「私はダメだ」と思ったら「それは本当か?」と自問自答してみることで、信念を見直すことができるはずです。
出来事はコントロールできない
出来事というのはコントロールができない。
つまり、
|
職場の人間関係も同じく。
|
結果がなかなかでなくとも仕事でミスをしてしまっても同じ。
そもそも自分の努力が足りなかったと気づきに変えてしまう。
|
ストレスに強い人とは出来事の捉え方をコントロールできる人であるのです。
今回のまとめ
というわけで、今回は以上です。
今回はストレスについて取り上げました。
同じ出来事でもストレスを感じる人そうでない人がいます。
心理学者のアルバート・エリスが提唱した認知行動療法のひとつ「ABC理論」で、
その仕組みをご紹介しました。
|
出来事というのはコントロールができないというのもポイントでした。
いかがでしたでしょうか?
最後まで読んでくださりありがとうございます。
少しでもヒントになればうれしく思います。