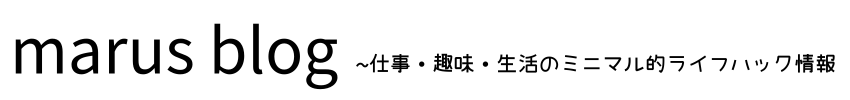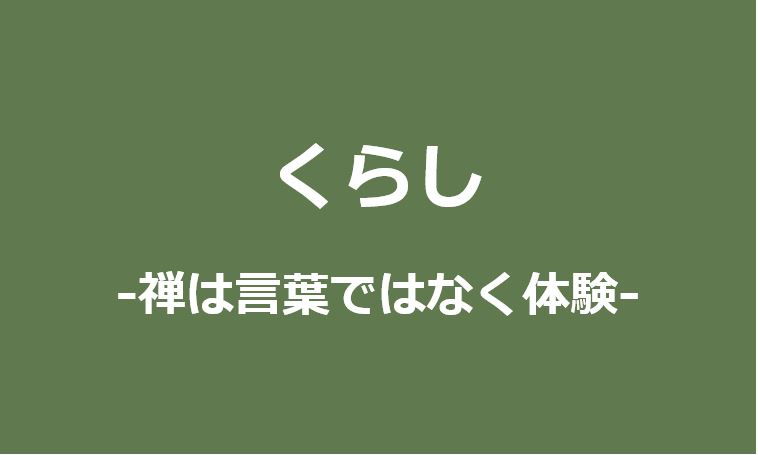
かのスティーブ・ジョブズ氏が日本の「禅」に傾倒していたことはよく知られています。外国人の経営者やデザイナーなどで禅に影響を受けたと公言する人も多いと聞きます。日本に暮らし仏教や禅とのつながりは他国の人よりも身近にふれているのに、その魅力や効力がよくわかりません。たまたま目にした書籍ダイジェストサービス「SERENDIP(セレンディップ)」で配信された京都妙心寺退蔵院副住職の松山大耕氏のコンテンツ。禅のことを知るきっかけになるようです。一部引用にて要約をご紹介します。
目次(ページコンテンツ)
禅は体験がすべて
禅は文字や言葉ではなく、実際の体験によってこそお釈迦様の本当の教えを体得できる。
世界のビジネスリーダーに広がる禅

本書は、世界のビジネスリーダーたちがたしなんでいる「ZEN」について。本来の禅の教えをもとに真の禅の教え、他の宗教や瞑想法との違いなどを分かりやすく解説。さらに、現代のビジネスにも応用可能な禅の仕方や実践について紹介されています。
また、今や欧米では「マインドフルネス」が、グーグルやアップルといった最先端の大企業で、経営や社員の研修に取り入れられ日本にも紹介されています。ビジネスZEN入門 (講談社+α新書)
マインドフルネスは仏教の瞑想法に由来しているところから、仏教、瞑想、禅、そしてマインドフルネスと同一視する人も多くいらっしゃるようです。
著者のプロフィールはこちら。
(プロフィール)
「1978 年京都市生まれ。2003年東京大学大学院農学生命科学研究科修了。2011年には、日本の禅宗を代表してヴァチカンで前ローマ教皇に謁見、2014年には日本の若手宗教家を代表してダライ・ラマ14世と会談し、世界のさまざまな宗教家・リーダーと交流。2014年世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に出席するなど、世界各国で宗教の垣根を超えて活動中」。
それにしても世界中でビジネスに禅が求められるのはなぜなのでしょう?
禅は文字や言葉でなく体験
禅について、副住職のコンテンツではこう解説していました。
「禅は文字や言葉ではなく、体験によって悟りを目指す」。禅は体験がすべて、日々の体験のすべてを禅は重んじている、それ自体が禅にとっては修行なのだと。
外国の方が禅の体験をすると、「なぜこんなことをするのだろうか」と疑問に感じられることが多いとエピソードも紹介されています。なぜ掃除がそんなに大切なのか、なぜ食事作法がこんなにも細かいのか。禅の本質をまだ理解していないからこその疑問というわけです。
使ったタオルをきれいにたたむ、脱いだ履物を揃える。禅は身近にあり、禅のある暮らしは、ほどよく、きちんと。生活を整えることで、心も整う。次第に禅が身近に感じるように思えてきます。
禅は言葉ではなく体験で教えを伝える、仏教との違いがここにあるようです。
人は倫理だけで動いていない
副住職の解説は続きます。
人はつらい仕事をしなければならない時もある。自分の意には反するけれどもやらなければならないこともある。倫理を越え理屈を超えたところで、即座に反応して行動ができるかどうか。
重要なのは理屈で考えるではなく、「まずやる」ということを重視しているのです。体験を繰り返し、まず実践する習慣を身につけること。そういう姿勢ですべてのものに向き合う。
理屈を超えたところで、即座に反応して適切に行動できるかどうか。体験を繰り返し、まず実践する習慣を身につけること。そういう姿勢ですべてのものに向き合うのです。著者の解説に、なにごともやる前に躊躇してしまう自分を反省してしまいます。
禅は、頭で考えるのではなく実践し、姿勢や身のこなしなど細かな一挙手一投足を正していく。
無駄なものは何も使わないシンプルさを重視
妙心寺の方丈南庭は本当にシンプルです。禅もシンプルなのです。
間と余白が注目される
著者が副住職を務める退蔵院は、外国の方が多くいらっしゃる。彼らはお寺の庭などをみて、よくその「間」または「余白」に注目されるそうです。これって日本文化独特の「わびさび」を感じているのでしょうか。
素朴さを感じる茶道具、静寂に包まれた庭園を見た時に感じる静けさ。「わびさび」の「わび」は内面の豊かさ、「さび」が表面的な美しさ。著者は、そこに見る人の気持ちが反映され、人の心を動かすと解説されています。
つまり、禅と心のありかたには深くつながっていると感じさせられます。
臨済宗妙心寺派大本山妙心寺のウェブページでは、「禅」をこう表現しています。
「禅とは 禅とは心の別名です」。
間や余白になぜ、そこに見る人の気持ちが反映され、人の心を動かすのでしょうか?
これ以上は何もいらない

それにしても、その庭は本当にシンプル。庭園に見る禅とのつながりを著者はこう解説しています。引用してご紹介です。
(~引用はここから~)
実際に妙心寺の塔頭・東海庵の方丈南庭があります。約100坪の長方形の空間には、ただ砂が敷かれ、まっすぐな線が引いてあるだけ。石も植木も何一つありません。
しかし、何もないのかといえばそうではない。塀の向こうには仏殿や法堂や松の木があり借景となっているし、庭には松の影が落ちる。
シンプルを極めた空間があることによって、それらのものが相互に影響を与えながら存在していることにきづかされるし、いろんなものが映えてくるのです。-京都妙心寺退蔵院副住職・松山大耕氏-
(~引用はここまで~)
庭園を思い浮かべるだけでも、そこに流れる静寂さを感じ取れます。無駄なものはいらないシンプルな生き方。心までが静寂に包まれ落ち着くような。心が楽になる、これも禅の体験で得られる変化なのでしょうか?
そうか、これでいい。これ以上は何もいらないのです。
禅と宗教、禅とマインドフルネスの違い
禅と宗教、禅とマインドフルネス、根本がまったく違うのです。
禅と宗教の違い
副住職は禅と宗教の違いの前に、キリスト教と仏教の違いにふれています。
キリスト教では、いいことを行っていれば神様が最後の審判でちゃんと救ってくれると教える。仏教はというと、いくら信仰しても仏様が救ってくれるわけではない。
お釈迦様は私たちと同じ人間。けしてスーパーナチュラルな存在を信じているわけではない。お釈迦様が”悟った”ということを信じているというのです。
なるほど、同じ宗教でもキリスト教と仏教は根本から違うのがわかります。スーパーナチュラルな存在を信じているわけではない仏教、禅とのつながりが少しずつ見えてくるようです。そして、言葉で伝える仏教と体験で伝える禅とは、明らかに違うと理解できます。
心の安定と幸せ、誰にとっても共通な願いをどうやってたどり着くのかが禅と宗教では違っているのです。
禅とマインドフルネスの根本からの違い
マインドフルネスと呼ばれる瞑想法が最近注目を集めています。禅とマインドフルネスは瞑想することが共通なので同じかと思いきや、本質がまったく異なると著者の解説に意外さを感じます。
マインドフルネスの瞑想は頭がすっきりする、心が落ち着くなど効果を求めている。禅はそうした効果を求めない。瞑想すること自体が目的だと。
仏教の曹洞宗には「只管打坐(しかんたざ)」という教えがあります。ただひたすら座禅をするという意味で、あの達磨大使が座禅をしてダルマになった逸話が有名です。ただひたすら座ってなんになると考えてしまいますが、それをすることが目的という考え方から禅が生まれてきたのが理解できます。
それにしても、禅はマインドフルネスのような効果は求めない、瞑想することが目的と言われても…。
一歩一歩の積み重ね
ただひたすら座る、ただひたすら歩く。
本当に大切なものはすぐには得られない。
「本当に大切なものはすぐには得られない。得ようと思っても得られるものではありません。また、遠くにあって大きく見えるものでもないでしょう」。そう話す著者副住職の言葉に返す言葉はありません。
さらに禅の本質へと解説が続きます。
(~引用はここから~)
一見何も得ていないように見える地道な一歩一歩の積み重ね。本当に大切なものは、自分の中に、自分の足元にあるのです。そこに目を向けること、すなわち自分の本質を見つめることの大切さ。それが、禅が教えてくれることなのです。
(~引用はここまで~)
禅の魅力に少しずつ近いづいている気がします。
禅が目指すのは心理学メタ認知を目標
副住職は最後に、禅が目指すのは心理学メタ認知を目標とすると最後のコメントにありました。
メタ認知とは、自分が認知していることを客観的に把握し、制御すること、つまり「認知していることを認知する」ことだとあります。参考サイト:メタ認知の概要(奈良教育大学)
副住職の最後のコメントはこちら。
(~引用はここから~)
禅では「論理」が否定される。倫理を「超える」と言った方がよいのかもしれない。我々は「倫理」の反対語が「感情」であると思いがちだが、禅では「感情」も「超えるもの」と捉えられているようだ。
無駄な感情を捨て、自分自身を第三者の視点から捉える。心理学では「メタ認知」として知られるこの視点こそが、禅が目指すものではないだろうか。禅の修行が究極のメタ認知を目標とすれば、少しでも禅に感心をもち、体験をすることで、メタ認知の世界に一歩足を踏み入れることができるだろう。それだけでも、ビジネスの心構えや行動、判断が変化していくに違いない。
(~引用はここまで~)
副住職は、禅の修行が究極のメタ認知を目標とすると明言されています。
私の感想
人生の後半戦乱れた生活を改めたく、禅僧の姿に心を惹かれて少しずつ禅を学ぼうと思うのですがなかなかどうして。正直、禅に関する書物を手にしても今ひとつよくわからない。やはり私には難しいと思っていました。
それでもマインドフルネスの瞑想法や、禅宗における座禅瞑想などを体験するものの、これまた中途半端でどうもいけません。禅になかなか近づけないのは原因があったように思います。
つまり、私は禅を頭で考えようとしていたことがその原因だったと。今回の副住職の解説に、頭ではなく体験をすることこその禅に、その奥深さをあたたかく感じられたような気がします。
今後は、禅的ライフへ一歩足を踏み入れようと思います。(2022年1月元旦)
(marusblog関連記事)
http://marus.info/200504zen/
http://marus.info/buddha-heart/
http://marus.info/stress21/
今回のまとめ
かのスティーブ・ジョブズ氏が日本の「禅」に傾倒していたことはよく知られています。外国人の経営者やデザイナーなどで禅に影響を受けたと公言する人も多いと聞きます。
禅はなぜ彼らを引き付けるのか。禅とはいったい何か。宗教となにが違うのか。そして、最近話題のマインドフルネス瞑想法と、同じく瞑想する禅とは何が違うのか。
書籍ダイジェストサービス「SERENDIP(セレンディップ)」で配信された、京都妙心寺退蔵院副住職の松山大耕氏のコンテンツで、奥深い禅のことを分かりやすく解説されていました。禅のことを知るきっかけになるのではとご紹介した次第です。
禅は文字や言葉でなく体験で教えを伝える。その教えは効果を求めるのではない。頭で考えるものでもなく実践することこそが目的であると宗教との違い。
禅はとてもシンプル。マインドフルネスの瞑想法は頭がすっきりする、心が落ち着くなど効果を求めている。禅はそうした効果を求めない。瞑想すること自体を目的としている。
ただひたすら座る、ただひたすら歩く。本当に大切なものはすぐには得られないもの。一見何もないように見える地道な一歩一歩の積み重ね。それは本当に大切なものは、自分の中に、自分の足元にある。そこに目を向けること、すなわち自分の本質を見つめることの大切さを禅は教えてくれる。
そして最後に著者のコメントには、禅が目指すのは心理学メタ認知を目標するとありました。その内容は、そのまま引用してご紹介しました。「メタ認知の世界に一歩足を踏み入れることができたら、ビジネスでも心構えや行動、判断が変化していくにちがいない」と、禅の魅力を伝えていました。
禅を知り、自分の本質を見つめ、心が軽くなるよう、今回の紹介記事が少しでもヒントになればうれしく思います。
いかがでしたでしょうか?
最後まで読んでくださりありがとうございます。人気ブログランキングに参加中。こちらクリックして頂けましたらうれしく思います。
↓↓↓
![]()
生活・文化ランキング